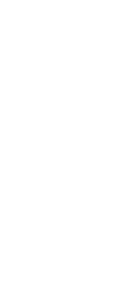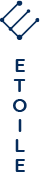- ブログ
インプラント治療で痛みを軽減するための麻酔とは
インプラントの治療では、2回法の場合2度の手術が行われます。手術と聞くと痛みが心配になる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、インプラント治療における麻酔処置ついてご紹介します。

インプラントの手術で痛みを和らげるには
インプラントは、むし歯や歯周病、外傷など何かしらの要因により歯を失った箇所を補う治療方法の一つです。顎の骨に埋め込まれるインプラントは、以下の3つのパーツにより構成されます。顎の骨にインプラント体(人工歯根)を埋め込むとき、そしてインプラント体と上部構造(人工歯)を結合するためのアバットメント(結合部品)を装着するときには外科手術を行いますが、手術中の痛みを軽減するために麻酔が使われます。したがって、基本的には手術中に痛みを感じることはありませんので、ご安心ください(麻酔の効き方には個人差があります)。
局所麻酔とは
処置を行う箇所の周囲だけに麻酔の薬液を浸透させ、その箇所の痛みを一時的に和らげる麻酔方法が局所麻酔です。全身麻酔のように意識を失わせる効果はなく、麻酔を効かせた箇所の感覚だけを一時的に麻痺させます。インプラント治療のみならず、むし歯の治療や親知らずの抜歯、深い歯周ポケットの歯石除去など様々な場面で局所麻酔は使われます。局所麻酔には、3つの種類があります。
・表面麻酔
歯ぐきの表面に塗って表面の感覚を麻痺させるのが、表面麻酔です。湿潤麻酔や伝達麻酔を入れるときには歯ぐきに注射針を刺して薬液を注入しますが、その際の痛みを軽減するためにあらかじめ表面麻酔で処置をしておくことがほとんどです。
・湿潤麻酔
歯科治療で行う麻酔として一般的によくイメージされるのが、湿潤麻酔です。歯ぐきに注射をして麻酔の薬液を入れ、骨まで浸透させます。
・伝達麻酔
麻酔が効きにくい下顎の奥歯や広い範囲に麻酔処置を行いたいときに行われるのが、伝達麻酔です。神経が枝分かれする前の部分に麻酔の薬液を作用させることで、広範囲に長時間麻酔の作用を効かせることができます。
局所麻酔によって起こりうる副作用やリスク
局所麻酔薬には「アドレナリン」とよばれる物質が含まれていますが、その副作用として血圧上昇や動悸などが挙げられます。特に、高血圧や心臓疾患をお持ちの患者様はこれらの症状が現れることがあるため、アドレナリンを含まない麻酔薬を用いることもあります。また現在使用されている局所麻酔薬は安全性が保障されているものですが、ごく稀にアレルギー反応を起こすことがあります。歯科治療で局所麻酔の処置をしたあとに気分が悪くなったことのある方は、事前に担当医までご相談ください。
麻酔処置後の過ごし方
麻酔が効いている時間は、湿潤麻酔で2~3時間、伝達麻酔で4~6時間程度です。麻酔が残っている状態で飲食をすると、熱いものでやけどをしたり、頬や舌を誤って噛んでしまうおそれがあります。麻酔がきれるまでは飲食はできるだけ避け、その後も常温のものや柔らかいものを中心に食べるようにしましょう。また、患部の再出血を防ぐためにも、血流を促進するアルコールや長風呂も極力控えてください。
麻酔がきれたあとは痛みが生じることもありますが、その際は処方されている鎮痛薬を服用しましょう。また、術後は安静に過ごすことが大切です。手術の前後に大きな予定は入れないようにお願いしております。
まとめ
このように、インプラント治療の際には局所麻酔の処置を行うことで痛みを軽減することができますので、ご安心ください。
当院では、インプラントの知識や治療経験が豊富な歯科医師が治療を担当いたします。治療に際して少しでもご不安な点や疑問点などがあれば、カウンセリングやご説明の際にお気軽にご相談ください。
執筆者情報

院長(歯学博士)
森蔭 直広Naohiro Morikage
飯田橋エトワール歯科医院のホームページにご訪問いただき、ありがとうございます。
当院では働く方でも通いやすいように、お昼休みの時間帯や土曜日の診療も行っております。また、安心して治療を受けていただけるように、徹底した衛生管理と高品質な治療設備を導入し、患者さん一人ひとりに合わせた適切な診断と治療をご提供できるよう心がけております。お忙しくてなかなか歯科医院に行けなかったという方も、ライフスタイルに合わせた短期間で正確な治療プランをご提案いたしますので、ぜひご相談ください。
経歴
-
2011年
日本大学歯学部総合診療科にて研修
-
2012年
日本大学歯学部口腔診断科学講座 入局
-
2013年
日本大学歯学部口腔診断科学講座 専修医
-
2014年
奥羽大学歯学部口腔外科学講座 臨床助手
-
2015年
都内開業医勤務
-
2018年
飯田橋エトワール歯科医院 開院
所属学会
- 日本口腔診断学会 会員
- 日本口腔顔面痛学会 会員
- 日本口腔外科学会 会員
- 日本口腔インプラント学会 会員
- 日本臨床歯科CADCAM学会 会員
- 日本アライナー矯正歯科研究会 会員
修了セミナー
[全顎的治療]
- Education for Oral Rehabilitation ベーシック・マスターコース(高橋登先生)
[アライナー矯正]
- アライナー矯正治療コース(尾島賢治先生)
[CEREC]
- CEREC Basic Course (風間龍之輔先生)
- CEREC道場(北道敏行先生)
- CERECコース(小池軍平先生)
[審美歯科、保存修復]
- ダイレクトボンディング ベーシック・マスターコース(高橋登先生)
- プレパレーションセミナー(岩田淳先生)
- C.R.E.Dセミナー(高田光彦先生)
- ADI 実践コース (二宮佑介先生、榊航利先生)
- Anterior&Posterior Restoration-2days Lecture(Marco Gresnigt先生)
[歯周病]
- JIPIぺリオコース(牧草一人先生)
[インプラント]
- Urban Regeneration Institute Advanced Hard and Soft Tissue Course(Istvan Urban先生)
- 水口インプラント道場 (水口稔之先生)
- ブローネマルク・コンセプトによるインプラント・コース(小宮山 彌太郎先生)
- SBICインプラントコース (中澤玲先生)
- 生体主導型歯科臨床セミナー (山道信之先生)